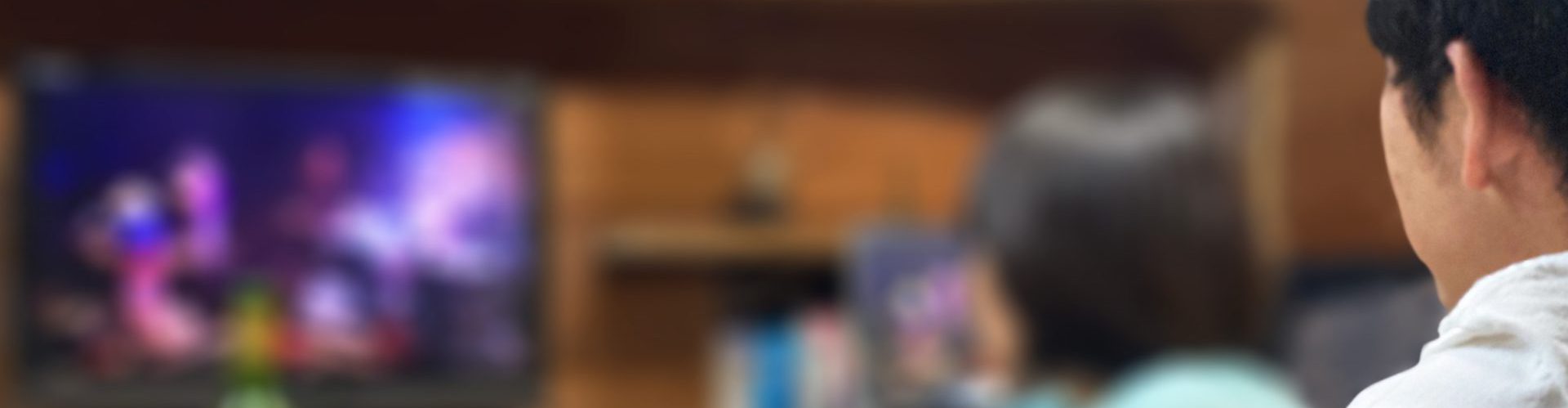お父さんの横顔
そろそろ、お返事をしなければならない。
先日、私は手袋屋さんの研修に参加させてもらった。高校の先生に勧められるままに決まった研修先で、短期間だったけど、学校と家の往復しかしていなかった私にはとても新鮮で、何より楽しかった。
「春から手袋職人の見習いとして、働きませんか」
まさか社長さんにこんなことを言ってもらえるなんて、今でも夢みたい。でも、私でいいのかな。ミシンで縫ったりと、細かいことをするのは好きだけど、それが仕事となるとやっていける気がしなかった。
「海香子、ぼんやりしてどうした?」
お父さんの声に、ハッとして顔を上げる。手元の茶碗から立ち昇る、サツマイモの炊き込みご飯のいい香りを胸いっぱいに吸い込むと、再び食欲がわいてきた。
「これからどうしようかなって考えてたの」
「晩ごはんを食べたら、久しぶりに映画でも見ないか?」
「えっと……、そうだね」
その「これから」じゃないんだけど。
うちのお父さんは仕事が忙しいので、なかなかいっしょに食事できない。けれど、たまに早く帰ってきた時には、決まってこうして誘われる。
「またアクション映画?」
「いいのがあるんだ」
食べ終わった私は、いったん自分の部屋に戻って、手袋屋さんの研修で作ったリストマフラーをつけた。最近、夜はほんとに冷え込むから、じっと座るような時にあると安心なんだよね。
「それ、きれいな色だな」
映画が始まって半時間。普段なら、お父さんは映画を見ている最中にしゃべることなんてないのに。
「好きな色を選んでいいって言ってもらったから、ラベンダーにしたの」
「そうか」
テレビ画面いっぱいに繰り広げられる非日常を眺めていても、「お返事」のことが頭から離れない。やっぱり、自信がない。でも、ベテランの職人さんみたいに、きれいな手袋が作れたらかっこいいだろうなぁ。それに、自分の作った手袋を大切な人達が使ってくれたら、きっと幸せな気持ちになれる。
「お父さん、私、手袋職人になりたい」
お父さんはチラリとこちらを見て、目を細めた。
「そうか」
「才能ないかもしれないけどね」
お父さんは、ゆっくりテレビに視線を戻す。
「でも、海香子はなりたいんだろ? 何かを決められるのも、一つの才能だと思うぞ」
おもしろいシーンでもないのに、横顔は笑ってた。
「何かを決めるだけで才能になるなら、みんな持ってるよ」
私にこれと言って得意なものがないのはお父さんも知ってるから、慰めてくれてるんだろうけどさ。無理にフォローしなくたっていいのに。
「いや、立派な才能だよ。一つ一つ決めていくうちに、きっと自分の知らない自分に出会えるよ」
お父さんは、それ以上は何も話さなかった。ただ、映画を見ながらニコニコしていた。
うん、やってみよう。
私はリストマフラーをつけた拳を、ぎゅっと握りしめた。